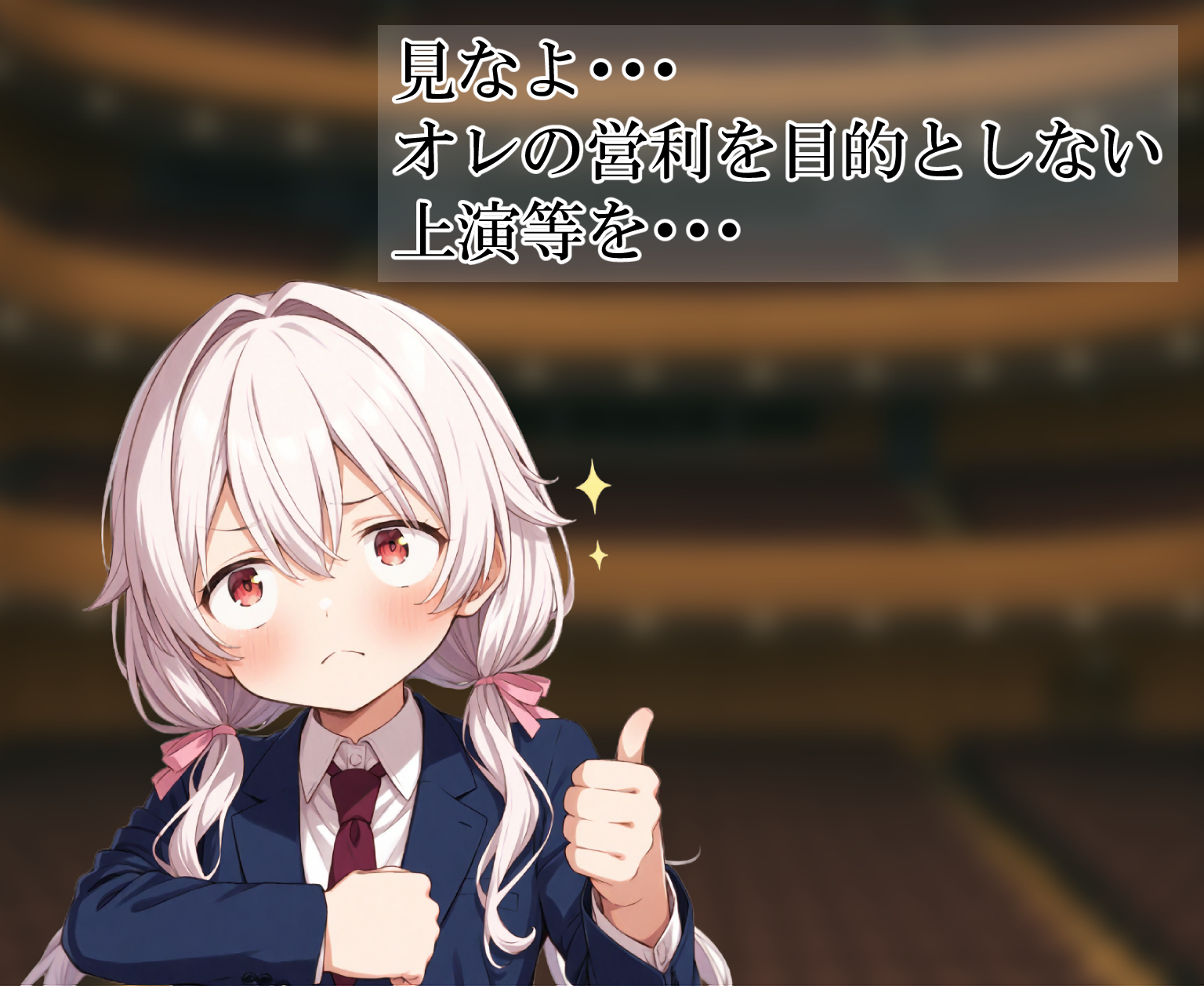条文
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
3 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
営利を目的としない上演等
本条の概要
本条は、営利を目的とせず、かつ聴衆または観衆から料金を受けない場合に限り、上演を始めとする様々な著作物の法定利用行為に対して著作権を制限する権利制限規定です。本条の対象となる著作物は公表された著作物(1項・4項・5項)と、放送または有線放送される著作物(本条2項・3項)です。上演、演奏、上映、後述などを始め幅広い支分権の対象となる著作物の利用行為が対象ですが公衆送信などは著作権者の利益を害する程度が大きいため本条の対象になっていません。そのため上演などを撮影・録画するなどしてその映像を公衆送信することはその上演が非営利無料無報酬で本条の権利制限の対象であっても適用されません。
非営利目的の上演・演奏・上映・口述(1項)
本条1項は、次の要件をすべて満たす場合に、著作物を自由に公衆に対して上演・演奏・上映・口述によって利用することができます。
①公表された著作物
②営利を目的としない
③聴衆または観衆から料金を受けない
④実演家または口述を行う者に対し報酬が支払われない場合
営利を目的としない
「営利を目的としない」とは、著作物の利用行為によって直接的・間接的問わず収益を得ない・収益に結びつくことがないことです。例えば企業の宣伝用の無料コンサートは例えコンサートが無料でも宣伝によって売上増加という利益につながるとめ本項の適用外です。ただし、構造改革特別区域法12条11項により学校設置会社(同法12条2項)について「学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合」に対しては本条1項が適用されます。そのため例え学校の学芸会などでも著作物の利用が無報酬無料であれば本項は適用されます。
喫茶店などで楽曲を再生することで間接的な事業促進になることも営利目的に含まれる。店舗での許諾の無いBGM再生が演奏権侵害となった裁判例もあります。
以後,この問題は,公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金を受けない場合には,公に演奏等することができるとする現行著作権法38条1項により規律されることになり,同項にいう営利目的には,楽曲の再生により利用者の満足度を高めるなど,間接的に事業を促進する場合も含まれると解されるから,平成12年以降,店舗のBGMとして楽曲を再生する等の行為は,著作者の許諾がなければ,著作者が専有する演奏権(著作権法22条1項)の侵害に当たることとなった(なお,特別な再生装置によらず,通常の家庭用受信装置を用いてラジオ等の放送をそのまま伝達する場合には,同法38条3項後段により,店舗におけるBGM利用であっても,著作権侵害とはならない。)。
(札幌地判平成30年3月19日〔理容所BGM事件〕)
デサフィナード事件では被控訴人がレストラン内の囲む会というライブに関して38条1項が適用されないことを主張し裁判所の判断によってこれが認められました。
著作権法38条1項の「営利を目的とせず」とは,間接的にも営利に結びつかない場合を意味し,デパートや喫茶店でBGMとして音楽を流す場合のように営業政策の一環として著作物が使用される場合には,観客や聴衆から入場料金を徴収しなくとも営利目的は認められるから,上記ライブ(囲む会)も営利目的であり,利用許諾が必要である。
(中略)
控訴人は,囲む会は入場料無料のプライベートな会であるから,「公の上演」(著作権法22条)に当たらず,かつ「非営利目的の上演等」(同法38条1項)に当たり,したがって,これに対する調査は正当な業務行為に当たらないと主張するようであるが,前記(1)認定事実に照らし,採用することができない。
(大阪高裁平成20年9月17日 [デサフィナード事件])
ダンス教室事件では、入会金とチケット代が音楽著作物の演奏に対する対価としての性質をも有するとみなされるとして、非営利とは認められませんでした。
法は,公表された著作物につき,①営利を目的とせず,②聴衆等から料金を受けない場合には,著作権に服することなく公に演奏等を行うことができる旨規定する(法38条1項)。これは,公の演奏等が非営利かつ無料で行われるのあれば,通常大規模なものではなく,また頻繁に行われることもないから,著作権者に大きな不利益を与えないと考えられたためである。このような立法趣旨にかんがみれば,著作権者の許諾なくして著作物を利用することが許されるのは,当該利用行為が直接的にも間接的にも営利に結びつくものではなく,かつ聴衆等から名目のいかんを問わず,当該著作物の提供の対価を受けないことを要すると解すべきである。
しかるところ,被告らが,本件各施設におけるダンス教授所において,受講生の資格を得るための入会金とダンス教授に対する受講料に相当するチケット代を徴収していることは前記のとおりであり,これらはダンス教授所の存続等の資金として使用されていると考えられるところ,ダンス教授に当たって音楽著作物の演奏は不可欠であるから,上記入会金及び受講料は,ダンス教授と不可分の関係にある音楽著作物の演奏に対する対価としての性質をも有するというべきである。
(名古屋地判平成15年2月7日〔ダンス教室事件第1審〕)
著作権法38条1項は,①営利を目的とせず,②聴衆又は観衆から料金を受けない場合で,③実演家等に対して報酬が支払われない場合には,演奏権が及ばないことを規定するところ,①の非営利目的とは,当該利用行為が直接的にも間接的にも営利に結びつくものでないことをいうものと解される。
上記1に認定した事実によれば,控訴人らは本件店舗の各店におけるバンド演奏によりバンド音楽を好む客の来集を図っているものというべきであるから,本件店舗の各店におけるバンド演奏による管理著作物の利用行為が,直接的にも間接的にも営利に結びつくものでなかったということはできない。したがって,本件店舗の各店におけるバンド演奏について,同条の規定する,演奏権が及ばない場合に当たるとはいえない。 控訴人らは,現SUQSUQにおけるセット代金は飲食代金であるとか,演奏する者がスタッフによる無料サービスであるなどと主張して,非営利性を主張するが,飲食店での客寄せのための演奏であることは自認しており,間接的に営利に結びつくものでなかったといえないことは明らかである。
(知財高裁令和元年9月18日 [Music Lounge SUQSUQ事件])
聴衆または観衆から料金を受けない
「営利を目的としない」だけでなく、聴衆や観衆などから「料金」を受け取らないことが必要となります。ここでいう「料金」とは、「いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。」と定義されています(法31条7項2号)。料金の額は指定されていないため微々たる額の徴収でも対価とみなされる場合があります。
料金は、入場料・会場費・会費等のいかなる名義をもってするかを問わないので、例えば学園際等において市価よりも廉価な料金ないしは実費を徴収する場合でも本項の適用外であり、権利者の許諾を必要とする。(中山信弘『著作権法 第4版』448頁)
例え、入場料が無料でも、会員制で会員費が演奏や上演への対価と解釈されれば「料金」に該当する場合があります。
本件各演奏会は,全体として一つの演奏会であって,第1部と第2部に分けることはできないし,平成11年6月27日開催分までについて,第1部は無料,第2部は有料という明確な区別があったとも認め難く,平成11年7月以降分に関しては,観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物の提供について受ける対価と認められる。
(東京地判平成15年1月28日〔ハートフルチャリティコンサート事件〕)
ただし、学校の授業料は一般的に教育に対して支払われている対価とみなされ、著作物の利用を目的としたものではないため、本条では「料金」とはみなされません。
また、④の「報酬が支払われない場合」については、著作権に対する使用料だけではなく実演家への報酬との間の平等性を保つための要件とされており、ここでは著作物の上演や口述などに対して実演家や口述を行う者に対して直接支払われる対価が該当することになります。なお、消防庁の音楽隊の隊員は、給与を受けていますけれども、それは、公務員として消防庁の職務に従事することについての一般的な意味における対価であって、演奏行進などの場合のその演奏を行うことについての報酬ではないという判断をいたします。一方、職業的音楽バンドの人が月給制の場合はどうかということになりますと、それはバンド演奏の対価として包括的に支払われている報酬であると理解するということであります。(加戸守行『著作権法逐条講義』,345頁)
なお、この「報酬が支払われない場合」という要件については、生演奏などに限定し録音録画を流す場合には無関係です。生演奏のように実演家によって著作物が演じられる場合にだけ意味がありまして、録音・録画物の再生による場合にはまず無視して差し支えありません。ここでいう報酬は、録音。録画する際の報酬のことではないからであります。(加戸守行『著作権法逐条講義』,345頁)
出所の明示・改変行為
本条1項の方法により著作物を利用するときに明示の慣行がある場合、合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければいけません(法第48条第1項第3号)。
法47条の6は38条に該当しないため、38条での著作物を改変して利用することは認められません。そのため非営利目的でも著作物を編曲した上での演奏は本条が適用外になり演奏権侵害の可能性があります。
非営利目的の放送・有線放送等(2項)
本条2項は次の要件をすべて満たす場合に、著作物を自由に有線放送または地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことを認めています
①放送される著作物
②営利を目的しない
③聴衆または観衆から料金を受けない場合
本条2項は、「放送される著作物」が対象となっており放送された著作物ではありません。
有線放送や自動公衆送信、つまり放送の同時再送信を対象とするものとされています。
本項による有線放送は有線放送による放送の再送信を対象としています。これには難視聴解消やマンション等の美観維持などの目的があります。有線放送は、もともとは山間僻地や高層ビルによる難視聴を解消するために利用してきたという経緯がある。放送は元来あまねく受信されねばならぬものであり(放送1条1号)、電波の届かない地域につき、無線で送られてきた放送の最後の部分に有線放送を用いるという意味合いが強かったが、やがて優先放送は放送に近い存在になり、位置付けも放送に近づいた。(中山信弘『著作権法 第4版』450頁)
一方で地域限定特定入力型自動公衆送信とは、「特定入力型自動公衆送信(法2条9の6)のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として行われるものをいう。」(法34条)と規定されていますが、 これは、難視聴対策等として限定されたIPマルチキャスト放送などという概念を放送と同等の扱いにするために付け加えられたものです。
非営利目的の受信による伝達(3項)
本条3項では、次の要件をすべて満たす場合に、著作物を公に伝達できると規定しています。
①放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物
②営利を目的としない
③聴衆または観衆から料金を受けない場合
④受信装置を用いて公に伝達すること
この場合に公の伝達権(法23条2項)は制限されることになります。
つまりここでは放送や有線放送等される著作物を公に伝達することに対して、大型プロジェクターなどを用いる場合に営利を目的とせず、料金を受け取らない場合に公の伝達権が制限されることとなります。ただし、「通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。」とあり、通常の家庭用受信装置を用いる場合は非営利・無料要件を満たす必要は無く営利・有料でも公の伝達権は制限されることになります。
本項で対象となっている放送同時配信(本条2項9の7)で規定されています。ここでは同時配信及び追っかけ配信を対象にしており、見逃し配信は対象外です。リアルタイムでの視聴ニーズを想定しています。
法第38条第3項については、多種多様な形態での公の伝達を認める規定であり、特に権利者に与える影響が大きいと考えられることから、「同時配信」及び「追っかけ配信」を対象としている(「見逃し配信」は対象外)
文化庁『著作権法の一部を改正する法律(令和3年改正)について』
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r03_hokaisei/pdf/93627801_01.pdf通常の家庭用受信装置を用いてする場合は例外で非営利・無料の要件は不要とされています。これは日常的視聴における利便性について考慮した規定となっております。ここで言う「通常の家庭用受信装置」とは一般的に普及しているテレビやラジオなどの家庭用の装置に限定されます。ただし、近年では高画質大画面のテレビ等も一般家庭で用いられているためその境界は曖昧なものとなっています。通常でないものというのは、例えば、影像を拡大する特別仕様のものや音の増幅機能を有するものなどを意味している。(作花文雄『詳解著作権法 第6版』393頁)
有線音楽放送を受けた喫茶店・バー等におけるお客への伝達行為については、店内の音響的効果を生かすようなスピーカーの設置等の実態からみて、有線放送自体における源泉処理を行うかどうかの実務上の問題は別として、形式的には、本項の規定の適用のないケースと解されましょう。(加戸守行『著作権法逐条講義』,349頁)
本項は著作隣接権には準用されないことに注意です。法102条には本条3項に規定はありませんので著作隣接権には準用されません。そのため放送事業者や有線放送事業者の著作隣接権であるテレビジョン放送の伝達権(100条)や有線テレビジョン放送の伝達権(100条の5)において、「影像を拡大する特別の装置」を用いる場合には非営利無料でも著作隣接権が及びます。
非営利目的の貸与(4項)
本条4項は次の要件をすべて満たす場合に、著作物の複製物の貸与により公衆に提供することができると規定しています。
①公表された著作物(映画の著作物を除く。)
②営利を目的としない
③その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合
4項では映画の著作物は含まず本条5項で規定されています。この項目は昭和59年改正で貸与権が新設された際に図書館が本を公衆に貸しだすことが例外になるための根拠となっています。非営利無料を要件に含むことは同じとして例えば会員制を採って、会費という名目でレンタル料相当額を徴収するような場合は、料金を受けたことになり、本項の要件を満たさないということでございます。(加戸守行『著作権法逐条講義』,350頁)
また本項では侵害物となるような著作物の複製物に対して4項は違法複製物(いわゆる海賊版)を除外していないので、違法複製物を非営利・無料で貸与しても本項に関する限り違法とならないが、違法複製物を情を知って頒布しましたは頒布目的で所持すれば侵害とみなされる(113条1項2号)。(中山信弘『著作権法 第4版』452頁)
映画の著作物の非営利目的の貸与(5項)
本条5項は次の要件をすべて満たす場合に、映画の著作物の複製物の貸与により頒布することができます。
①公表された映画の著作物
②a.映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの
b.聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で37条の2の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)
③その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合
映画の著作物には貸与権が設定されていませんので本項では貸与のための頒布権を制限する規定となっています。頒布の内容には映画の著作物の複製物を公衆に提示することを目的として譲渡し、または貸与することを含むものとする。(法2条1項19号)と規定されていますので頒布には貸与も含まれるからです。
第5項は、前項において貸与権の制限が規定されたこととの関連で、昭和59年の改正で設けられた規定でありまして、映画の著作物についても、視聴覚教育施設等政令で定める非営利目的の施設や聴覚障碍者等の福祉に関する事業を行う者として政令で定めるものによる無料の貸与について頒布権を制限したものであります。(加戸守行『著作権法逐条講義 七訂新版』350-351頁)しかし、これは従来頒布権が及んでいた分野について新たに権利制限を行うものであるところから、権利者の利益を不当に害することのないよう、貸与を行い得る施設を政令で限定するとともに、相当な額の補償金の支払を義務づけております。(加戸守行『著作権法逐条講義 七訂新版』351頁)
本条5項では同条4項と異なりの貸与の主体が決められています。a.では著作権法施行令2条の3の映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設で規定されている「国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設」、 「図書館法第2条第1項の図書館」、 「前2号に掲げるもののほか、国、地 方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚 資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文 化庁長官が指定するもの」である。
b.では著作権法施行令2条の2の聴覚障害者等のための複製等の1項2号で認められる者で規定されています。「大学等の図書館及びこれに類する施設」「身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(施設を設置する者は国、地方公共団体または一般社団法人等に限定)」「図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているもので施設を設置する者は地方公共団体、公益社団法人または公益財団法人に限る。)」「学校図書館法第二条の学校図書館」そのほかにも「聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの」です。
また映画の著作物の頒布を行う者は、映画の著作物または映画の著作物において複製・翻案されている著作物につき頒布権を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならないことが本条5項後段で明記されています。「相当な額の補償金」とは利用に見合った額、つまり使用料相当ということになります。
参照文献
加戸守行. (2021年12月21日). 著作権法逐条講義(七訂新版). 公益社団法人著作権情報センター.
作花文雄. (2022年12月20日). 詳解著作権法[第6版]. 株式会社ぎょうせい.
小泉直樹他. (2019年3月11日). 著作権判例百選(第6版). 有斐閣.
小泉直樹茶園成樹,蘆立順美,井関涼子,上野達弘,愛知靖之,奥邨弘司,小島立,宮脇正晴,横山久芳. (2023年6月15日). 条解著作権法. 弘文堂.
斉藤博. (2014年12月26日). 著作権法概論. 勁草書房.
中山信弘. (2014年10月25日). 著作権法(第4版). 有斐閣.
文化庁著作権課. (日付不明). 令和5年度著作権テキスト.